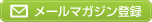終活とは
終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語で、残された人生の終末をより良く迎えるために、自ら積極的に準備し、より自分らしく生きていくための活動のことをいいます。

「終活」とは、自らの死を意識して、死に対してただ恐れるだけでなく、残りの寿命と真摯に向かい合い、人生の終末をより良く迎えるために、自らお墓や葬儀などの準備、生前整理や遺言書を作成するなど人生の終焉に向けて積極的に準備することです。
終活を行うことにより、残されるご家族への負担を減らし死後の不安を軽減させることで、残りの人生を充実して暮らせるようにするための前向きの活動のことをいいます。
終活をおこない進めていくなかで、家族に自分の意思が伝わり、老後を安心して楽しく過ごせます。また、ご自身がお亡くなりになられた場合に備え、準備をすることで、残された家族の負担を大幅に軽減することができます。
近年の日本では、少子高齢化、こと団塊世代の高齢化が進んでおり、それに伴い、老後生活の心配の解消や遺された家族の負担の軽減のために、終活を始めようと考える高齢者が増加しております。
他にも、終活の一環として生前に準備しておくと良いのは、エンディングノートの作成や生前整理、遺言書の作成、葬儀の備えなど、多岐にわたります。
延命治療の有無や臓器提供や検体を希望するかなどの医療面や、介護への要望なども元気なうちに意思表示することも終活の一貫であり、意思を伝えておくことで残りの人生を心安らかに暮らすことができます。
 また、「終活」の一環として自分の人生を見つめ直すことで、これからやらなければならないことや明確に分かってきます。
また、「終活」の一環として自分の人生を見つめ直すことで、これからやらなければならないことや明確に分かってきます。
そして、「終活」を行うことで下記のようなメリットが得られます。
終活で得られるメリット
「 残された人生が豊かになります 」
終活をおこなう中で、今までの人生を振り返りご自身の終焉を考えることで、残された時間に何をするべきかが明確になり、残りの人生を充実したものにすることができます。
また、残された人生への不安や悩みなど、自分の心の中にある全てのものを整理していく過程で、気持ちがスッキリしてきます。
さらに、事前にお亡くなりになった後のことについて決めておくことで、将来の不安が軽減されます。
「 家族や大切な方の負担の軽減 」
あなたがお亡くなりになった後のことを何も決めておかないと、遺されたご家族にとって大きな負担となってしまいます。
終活の一環として、相続の問題や葬儀やお墓の準備、介護・医療の希望など、元気なうちにこれから将来起こると予想される様々な問題や課題に対して準備することで、遺される家族や大切な方への負担を大幅に減らすことができます。
「 相続トラブルが避けられる 」
お亡くなりになった後に、ご家族間で遺産相続を巡りトラブルが起きることは避けたいところです。
そうならないためにも、終活の一環として遺言書を作成しておくことで、遺された家族同士の遺産相続を巡る争いを避けることができます。
「 ご家族と想いが共有できる 」
終活をおこない、ご自身の意志と希望を明確にしておくことは大切です。
出来れば、終活は自分ひとりでおこなうのではなく、家族や周囲の人と一緒おこなうことが望ましいです。
終活をご家族と一緒におこなう中で、ご家族と懐かしい思い出話しをしたり、ご自身の希望や想いを明確に伝えることができるので、ご家族と希望や意志が分かりあえ、お互いの想いを共有することができます。
もし、ご家族と一緒に終活ができない場合は、自分の考えや希望、ご家族への想いをエンディングノートなどに記載して明確に伝えておくだけでも安心感が得られます。
このように終活を行うことで多くのメリットが得られます。
次に、終活とはどのようなことをするのかについて説明したいと思います。
終活でやることは多数ありますが、主にやることは10の分野(エンディングノート、お墓・墓地・霊園、葬儀、相続・遺言、生前整理(断捨離)、介護、住宅リフォーム、仏壇・仏具、保険、旅行)になります。
その10の分野の中でも、終活としてまず最初にやっておきたいのが「エンディングノートの作成」です。